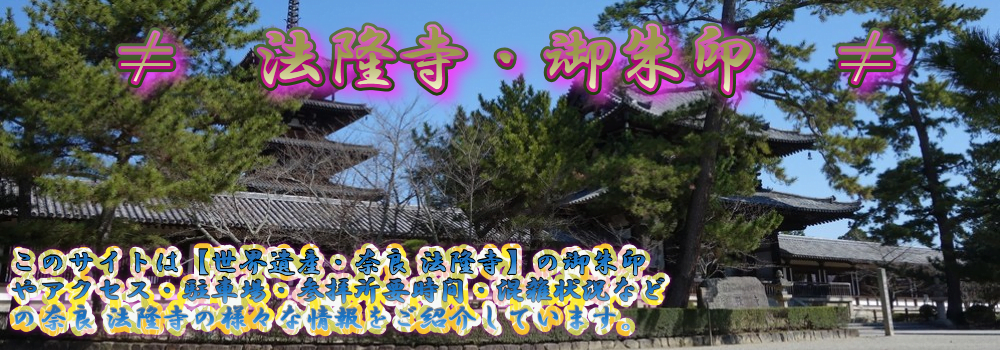『よし!みんな!修学旅行に行ったら俳句を作ってくるんだぞ!分かったな!!』
・・などと言って、突然の俳句作りの宿題を出されて困っていないだろぅか?
俳句作ってやるわぃ!!‥‥という気概を以って現地に臨むことで、後々の俳句の出来栄えも大きく変わってくることだろぅ。
心構え一つ変えるだけで、通常では味わえない表現を思い付くかもしれなぅい。
まずは、法隆寺を現す代表句はコレ!
法隆寺を代表する俳句と言えば、真っ先にこの俳句が出てきます。
『 柿くへば..鐘が鳴るなり..法隆寺 』
あまりにも有名だが、作者はもちろん知っているな?
そぅ!作者は「正岡子規(まさおか しき)」。
子規は江戸時代に「俳諧(はいかい)」と呼ばれていたものを「俳句(はいく)」と名付けて俳句ブームを素敵に巻き起こし、業界の先覚者として時代を先導しつづけたと、これまた素敵に伝わ〜る。
正岡子規が中心となった俳壇(グループ)では、「写実的な表現(写生)」を重視した数々の新たな俳諧スタイルを生み出した。
その中の秀作と呼べるものの一つが、上記の俳句「柿くへば‥」とな〜る。
法隆寺の俳句の作り方の基本
ではここで正岡子規の俳句を使って、学校で習った俳句のキホンや表現技法をおさらいしてみましょう。
「柿くへば」の意味
「柿くへば」は「五音」です。
そして、「柿」は秋の季語ですね。
現代の俳句では、季語は絶対ではありませんが、特に情景を詠む場合は、あった方がいいでしょう。
「柿」と言うだけで「時期は10月末から11月にかけてです」という事実だけでなく、「過ぎた夏」、「もうすぐやってくる冬」といった季節のうつろい、肌寒さや物悲しさなどの、イメージまで喚起させられるわけです。
「くへば」の意味
「くへば」は、この俳句の場合、単に「食べたら」くらいの意味です。
「鐘が鳴るなり」
次は「七音」です。
五感の中のいずれかの要素が入ると、読者のイメージを膨らませられる俳句になります。
さっき柿が口に入ったところでしたから、これは味覚も聴覚も意識した俳句になっているということですね。
休憩にと立ち寄った茶屋で柿を食べているという、もっとも身近な視点と、町中に響く鐘の音を並べることで、空間的にも広がりを持ったイメージが浮かびます。
「なり」は切れ字として、意味を区切り、「詠嘆(えいたん/深く感激すること)」を表す役割を持っています。
「や」「かな」「けり」なども同じです。
「法隆寺」
最後は「五音」ですね。
ということで、「五・七・五の定型の俳句」でした。
中には、「字余り」「字足らず」「自由律」の俳句もあります。
名詞で終わるのは、「体言止め」という表現技法でしたね。
「インパクト」や「余韻」が大きくなります。
今まで柿の味や食感、鐘の響きや、その音が降り注ぐ静かな町を思い浮かべたわけですが、ここで読者は初めて急に立派な法隆寺の伽藍をハッキリきりきり‥とイメージします。
なんとな〜く、この十七音のストーリーがキレイにまとまった感じがしませんか?
ここまでストレートでなくても、景色や場所を詠み込むと俳句の詠まれた場面を視覚的にイメージできて良ぃのではなかろうか。
法隆寺の俳句を作る際の「ネタ集(素材集)」
おぃ!そこの学生共!
お前たちが法隆寺に行って素敵に俳句を作りやすくするために、本項では「五・七・五」で詠みやすい法隆寺の景物や文化財、法隆寺にまつわる季語などを以下に列記する。
🌸「春」の季語
- 「桜」
- 「朝桜」
- 「夕桜」
- 「夜桜」
- 「しだれ桜」
- 「彼岸桜」
- 「糸桜」
- 「入学式」
- 「卒業式」
- 「入社式」
- 「新入生」
‥‥以上、どんな言葉を選んでも構わないが、法隆寺らしさを表出すべく、以下にワぁタクぅシぃメが作成したお手本を用意した。
こホンっ!…それではココで「春を題材とした渾身の一句」
『 風が吹き シュウマイ落とした また食べる 』
『 ホぉぅホケきょ おにゅうの制服 さくら道 』
『 ポテチ〜と カールと えびせん 映画館 』
‥‥ドコが春じゃぃ!なんとかカスとっとるのが一個だけや!
こホンっ!…それではココで「法隆寺を題材とした渾身の一句」
『 花吹雪 芳香に誘われ 法隆寺 』
『 グリーン豆 塩味パリポリ もぅ止まらん 』
『 斑鳩に 望郷の夢 風そよぐ 』
『 昼下がり ○ナニー没頭 エ○動画 』
『 サイゼリア ワイン3本 まだホロ酔い 』
‥‥‥ドコが法隆寺の俳句じゃ!かろぅじて絡んどるの上と真ん中の二つだけや!
☀️「夏」の季語
- 「安居(あんご)」
- 「夏籠(げごもり)」
- 「夏行(げぎょう)」
- 「松落葉」
- 「散松葉」
- 「お盆」
- 「盆踊り」
- 「冷房(クーラー)」
- 「かき氷」
こホンっ!…それではココで「夏の法隆寺を題材とした渾身の一句」
『 カブトムシ ミヤマクワガタ カブトムシ 』
『 コガネグモ ラムちゃんピチピチ 思い出す 』
『 真夜中に 秘密を通って 今、月夜 』 …分かる人に向けての特ネタ
『 女子バレー 女子バスケに チアガール 』
‥‥‥ナメとんのかワレ。
「秋」の季語
- 「彼岸花(曼珠沙華)」
- 「柿」
- 「甘柿」
- 「渋柿」」
- 「紅葉(「もみじ」や「こうよう」「モミジ」とも読む)」
- 「盂蘭盆」
- 「盆会」
こホンっ!…それではココで「秋の法隆寺を題材とした渾身の一句」
『 適温に 心を許し 今日、大食い 』
『 鹿せんべい 酒のツマミに ついついと 』
『 小指にて 鼻くそホジホジ 大活躍 』
『 からあげくん トンビに取られた コンちくしょー 』
『 ウンコ踏み 靴を洗って 法隆寺 』
‥‥‥ワレほんまにナメまわしたろかぃ…
⛄️「冬」の季語
- 「正月」
- 「節分」
- 「みかん」
- 「こたつ」
- 「コート」
- 「ちゃんちゃんこ」
こホンっ!…それではココで「冬の法隆寺を題材とした渾身の一句」
『 雪だるま あぁ雪ダルマ 雪だるま。 』 …「雪ダルマ」連発で言うとるだけやないけ!
『 ハイボール 飲み過ぎ下痢便 止まらない 』
『 クロミさん あぁ…クロミさん クロミさん 』
『 サンリオファン 酒好き多ぃ なぜだろぅ 』
『 抜け出せん ネトゲとコタツ 法隆寺 』
『 甘い罠 妖艶 君のクチビルと 』
『 カラオケは あっという間に 1時間 』
‥‥‥。‥‥。‥カ〜っ!
その他の法隆寺を題材とした俳句で使えるネタ
- 「法隆寺」
- 「五重塔」
- 「金堂」
- 「夢殿」
- 「子規」
- 「太子」
- 「薬師如来仏」
- 「仁王像」
終わりに・・
法隆寺に行ったら五感を総動員して、ぜひ納得のいく一句を詠んでみよぅZE!
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。