あまり、多くの方はご存知ではないですが、奈良・法隆寺には、「ノコギリ(鋸)」と「鎌(かま)」に関わるような、ちょっとしたお話があります。
奈良 法隆寺の「鎌(かま)」
法隆寺には、鎌に残された伝承があります。
しかし、鎌といっても手に持って草などを刈り取る鎌ではなく、なんと!法隆寺の西院伽藍の五重塔の上に鎌があると言うのです。
詳しくは、五重塔の頂の上に立つ相輪に添え付けられており、一説には、これは鎌ではなく、避雷針の役割りをしているとも云われております。
ただ、拡大した写真や画像を見てみると、あきらかに「鎌」そのものであることが分かります。
しかし、この鎌がいったいなぜ、このような場所にこのように添え付けられているのかは、今に至っても謎と云われております。
法隆寺の鎌が解明!!「驚くべき真実」
鎌といえば名工の仕事でもあります。
ましてや、法隆寺という歴史的な寺院ともなれば、それなりの名の知れた名工と契約をしていてもおかしくはありません。
実は法隆寺には、取引きをしていた鉱物の鍛錬所があって、その鍛錬所の名前を「水野鍛錬所」といったそうです。
この鍛錬所は、堺にある鍛錬所で、当時の法隆寺の座主(管長)であった法隆寺123世管長「佐伯定胤(じょういん)管長」と懇意の仲であったそうです。
その水野鍛錬所には、なんと!佐伯定胤管長が自筆で書いたとされる古文書が残っているとのことです。
その古文書の中には、法隆寺の相輪の鎌についての、重要な手がかりとなるような以下↓のような一文が見つかったとのことです。
しかし、幸いなことに境内にいた大工4名が決死の覚悟で火を消し、一命を取り留めた。
その後、皆を集めて対策を練った。
その対策とは、御札を五重塔の各階(各層)にお祀りし、雷除けのために、鉄製の鎌を4本作り、これを相輪の下の方へ四方の方角へ、ニラみを効かせるように付けた。
その後、600年経った現在(昭和22年)、鎌が1本になってしまった。
このままでは、何か心許ない気持ちで不安が残る。
よって、この度、近く行われる境内の大修繕で、もとの4本の鎌に戻すことを決意し、堺の名匠である水野家の水野正範に鎌の制作を委ねるものとする。
・・と、いうような記載があったそうです。
法隆寺の相輪の鎌の由来・意味とは、雷に対して鎌で威嚇して雷を落とさないようにとの、意味合いのような一種の呪い(まじない)が込められているようです。
ちなみに、この時、鎌は8本作られたそうです。
さらに、特別に古の鍛錬の方法で繰り返し繰り返し鍛錬を重ねてようやく完成したそうです。
現在、8本に内、1本は、水野鍛錬所の家宝として大切に保管されているようです。
現在の水野鍛錬所の当主は、これを知った時こう言ったそうです。
『この鎌は300年ごとに取り替えをしていたそうですが、今後は未来永劫、五重塔の頂で一際、光輝く「法隆寺のシンボル」となるでしょう』と。
法隆寺の鋸(ノコギリ)
法隆寺のお堂などの建築様式を見て、驚かれた方も多いと思います。
エンタシスを始めたとした、建築様式は目を見張るものがあります。
しかし、肝心なことに疑問が湧いてくる方いると思います。
「どうやって木を切ったのか?」
法隆寺の建築物は、キレイに確実に建造されているイメージがあります。
しかし、驚くことになんと!法隆寺の創建当初にはノコギリなんて便利な道具はなかったのです。
では、どうやって木を加工したのか?
と、いった疑問が湧いていまいますが、法隆寺の建築物は木を切ったのではなく、「割った」と言う方が正しいのです。
つまり、おおよその設計図があって、その図面通りの寸法に木を割って、後は手作業で削ったりして形状を整えていくのです。
こうして1つの建家ができていくのです。
削る道具は「釿(ちょうな)」「槍鉋(ヤリガカンナ)」などの道具を使用して削り形状を創作します。
一方、木材を割る道具とは、「大斧」「ノミ」が使用されたと云われています。
当時では、木材を加工する技術が乏しかったので、より良質な木材を使用する必要がありました。
よって、現在の法隆寺が数千年もの間、姿を留めているのは、まさに良質な素材と職人たちの技術に他ならないといったことになります。
関連記事一覧
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。
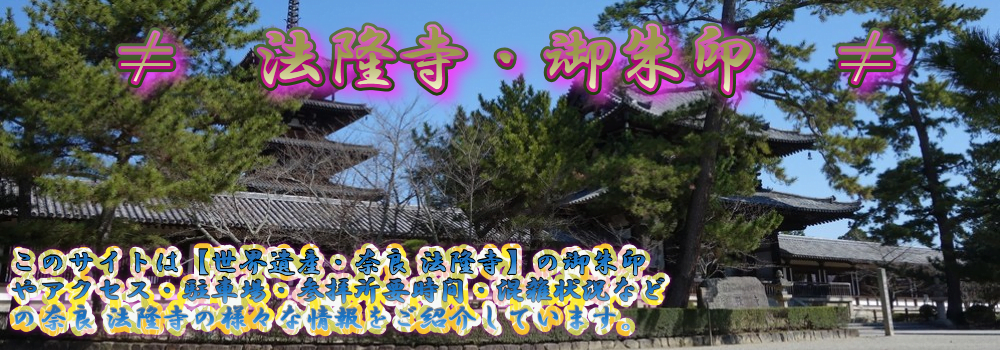
」.jpg)
」「槍鉋(ヤリガカンナ)」などの道具を使用して削り形状を創作します-2.jpg)
」「槍鉋(ヤリガカンナ)」などの道具を使用して削り形状を創作します.jpg)